�@�@
�@�m�Ԃ͓��a�R���O�ŁA���̋���r��ł��܂��B
�@���܂̂��܂��Ԃ��ʂ炵�Ă��܂��قǂł���Ɖ�����Ă��܂��B
�@�����A���a�R�ɍs���܂ł́A���̂悤�ɉ��߂��Ă��܂����B
�@�������A���O�̌�_����g�������đ̌�����ƁA
�@�m�Ԃ������Ă�����i�͑S���v�������ׂ邱�Ƃ��ł����A
�@�Ⴄ���R���Ԃ��ʂ炵�Ă�����i�����肠��Ɩڂɕ����т܂��B
�@�����āA�K�ӂގQ���ł́A��������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ������Ƃ��āA��w�������܂��B
�@����D���Ƃ��āA�ʂ̉��߂ɂ��ǂ���܂��B��𓊂������B
�@���̓��a�ł̔m�Ԃւ̃C���[�W�ł��B
�@�Ⴆ�A�m�Ԃ���_�������Ɋ܂L�^�͂���܂��A
�@�ے���ł��Ȃ����Ɠ����ȉ��A�C���[�W���Ă��܂��B
�i�m�ԁj
�@�]�ǂ�A�_���ȓ��a�A��͒u���Ă����A�����ɂȂ�A��_�̂Ɏ�����āI���Q�肳���ƁA�������B
�@�ł́A������ɍs�����A�����]����������~�߂Ă���B
�i�]�ǁj�@�@
�@�Q���ł́u���a�R�@�K���ޓ��́@�����ȁv�Ɖr�悤�ɁA������Ȃ����ǁA
�@���a�ł��������Ȃƌ���ꂽ��A���A�]�������܂���`�A
�@�ł��A������낾����A�t���������Y���ɂ��邱�Ƃ͂���܂���B
�@�t���������Ă�����A�~�߂܂����A���a�����𗣂����u�ԁA�ꏏ�ɗ����܂���B
�i�m�ԁj
�@���a�͗����ɂȂ��āA�����ꗎ���Ă����_�̂̊�̌��O�ɓo��Ȃ�āA�Ƃɂ��������I
�@���a�̌�_�̂̓o��͂��߂����X�������I��_���ɑ����Ƃ��āA���������炷�ׂ藎�������B
�@�]�������Ȃ��悤�ɁA���a�̌�_�̂ɂ�������ƉE�A���ƌ��݂Ɏ�����āA�����œo���Ă����̂��B
�@�����̗��ƁA��̕��Ɍ�_�����u�M���A�M���v�ƒ��ɓ`����Ă���B
�@��z��ł͂Ȃ��A�z��O�̍����B
�@�����Ǝ蓒���ɂ��Ă��������A�S�g�����錌�t�ɂ���āA�S�g���ۂ��ۂ�����B
�@��_���ɑS�g�����Ă���̂Ɠ����A�Ăɉ���ɐZ�����Ă���킯������A�M���Ȃ��Ă����B�@
�@�]�ǂ�A�K�ӂގQ���ł́A��������Ƃ͂ł��Ȃ����ǁA
�@���R�́A��_�̂Ɏ�ŐG��邱�Ƃ��ł���̂���A�Ȃ�Ƃ�������ł͂Ȃ����B
�i�]�ǁj
�@�Q���ŁA���������Ă���������A��������ĂƂ܂�܂���A�t���B
�@����ɁA�t�����Ԃ���H���_�����A���̊�ʂɂ���āA�����̟��ƌ�_���ŁA��ʂ��ԔG��ł��B
�i�m�ԁj
�@���a�𗬂ꗎ���Ă������ɁA����������a�ɐڂ����Ԃ�G�炷���ƁA�G�炷���ƁA
�@�������Ԃ��A���a�̌�_���ɂ��ԔG��ŁA���肪����A���肪����B
�@���a�ɑf���œo��A���a�̌�_�����Ԃ�G�炵�A�Ȃ�Ƃ������I�Ȃ��Ƃ�B
�i�m�ԁj
�@���a��o�肫��ƁA��������ɗ����Ƃ��ł���ˁB
�@���O��ڂ̓�����ɂ���ƁA�����I
�@�����ł���܂łɂ͐_��̔N�����o���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA����܂��������̂��Ȃ��B
�@���a�ɑf���Őڂ��A�������Ԃ����_�����������藎���Ă�����A���߂Ċ����I
�@�������łĂ����A�Ԃ͌�_���ł��ԔG�ꂾ�����̂ŁA����̉����Ŗڂɟ��݂邵�A�����ԂŐ@��Ȃ���B
�@������_�̂ɗ����A��_���ƈꏏ�ɂȂ��āA���ꗎ���Ă�������B
�@�G�ꂽ�Ԃ��炵�������_���𖡌�������A�S���ŁA�������B
�@���a����ɂ��Ă���A�G��Ă����Ԃ������ƁA�Ԃ����܂��Ă���A���a�̌�_���͂Ȃ�Ƃ��͋����Ȃ��B
�@���a����ɂ��Ă�����A�Ԃ����܂����Ԃ�����ƁA�������S���Ă����B
�@����ʓ��a�Ȃ̂ŁA���O���̂��̂̌`�ɂ��Ă͌���Ȃ����ǁA�Ƃɂ������������B
�@�u����� ���a�ɔG�炷 �Ԃ��ȁv���̋�ɁA���̊��������ׂĂ��߂��B
�@���a�����Q�肵���l�́A���̋傩��A���̑̌��������i���v�������ׁA
�@�����̑̌����N���ɔ]�����S���Ă��邱�ƕK��A�ǂ��傪�ł�����B
�������
�@�m�Ԃ́A���̋�ɂ��߂������ЂƂ̐^�ӂ������܂��B
�@�]�ǂ��Q���Łu���a�R�K�ӂޓ��̟����ȁv�Ɵ����Ă��܂����A
�@�m�Ԃ��u�Ԃ��ʂ炷�v�Ɖr�̂ŁA�×����犴���ɗ܂���Ɖ��߂���̂�������O�Ǝv���܂��B
�@���O�����ĂȂ��l�́A�����ɗ܂�����ł��˂Ɗm�M����ł��傤�B
�@�������A���a�̌��O�������҂́u��閳����v�A���ĂȂ��҂́u����������v�̉���������̂ŁA
�@���R�͂���Ȍ`���Ă��āA�Ă���̕�����M����_�������ӂ�o�Ă��āA
�@��_�̂ƌ�_���ɒ��ڐG�ꂽ�������A�Ԃ��G���ƕ\�������Ɣm�Ԃ͌��܂���B
�@�ł��A�����Ԃ͔G��Ȃ��������ǁA���ہA�������ł��傤����A�������߂��Ă�����Ă��������Ă���傾���A
�@�������߂����ł��낤���Ƃ��A�m�Ԃ͑z�肵�āA���Ȃɐ��Ȃ��d�˂ĉr�傾�Ǝv���܂��B
�@������A����͂���ŗǂ��Ɣm�Ԃ͎v���Ă����Ǝv���܂��B
�@���O�����Q�肵���l�Ȃ�A�ʂ̉��߂����āA�m�Ԃ̊������킩�������Ă����Ɗm�M���Ă����Ɛ������܂��B
�@�]�ǂ́A���R�̊������A��閳����̉����̒��A�ǂ��`���悤���Y�݂ɔY�݁A
�@��_�̂Ɏ�ŐG��Ă��Q�肷�铒�a�̂��Ƃ͌����Ȃ�������A
�@�Q���ł͎�����Ă͂����Ȃ��Ɖr��ŁA���O�̊�����U�Ȃɕ\�����Ɖ��߂��܂��B
�@�]�ǂ́A�ߐ{���{�ŁA�����T���A����̗N�o�ʂ�N�o�n�A���L�^���Ă��܂��B
�@�U�J�����ׂẲ���ׂĂ��܂��B���ɉ���}�j�A�ł��ˁB
�@�u�ȏ㓒���Z�����B��n�o�����s��A���n��A�\�m���n���⌓�A�䋴�m����B�\�m���n�s�o�B�\�m�������A�c�V�B
�@�\�m���A����m�R�A���m�]��B�v
�@�U���Ƃ́A�s�l�̓��A���̓��A�䏊�̓��A��̓��A���̓��A�͌��̓��ł��B
�@�܂��A���̍ד��ł͍̑�����Ȃ������u�����ނ��Ԑ��Ђ���������v����������Ɠ��L�ɋL�^���Ă��܂��B
�@�ߐ{���{�̉���Ɏ�����đ]�ǂ����������͂��ł��B���a�̉���Ɏ�����������́A���̔�ł͂Ȃ��͂��B
�@����}�j�A�̑]�ǂ��A�ߐ{���{�ł���قnj���̑f��������Ă���̂ɁA���a�̉���̑f���͌��Ȃ��B
�@����}�j�A�̑]�ǂ��Ƃ�s���́A��_���Ɏ��G��āi���G��Ȃ��Ɠo��Ȃ���ł�����ǂ��ˁj
�@���m�F�A�N�o�|�C���g�ƗN�o�ʂ��m�F�A���������Ă���͂��B
�@�m�Ԃ͑����G�ꂽ�Ɖr��ŁA����������Ƃ��Î����܂������A
�@�]�ǂ́A������āA��_�������`����Ă��������Ɗ������A�Q���ł͎�����Ȃ��Ɖr�ނ��Ƃɂ���āA
�@����D���̎��ɂ́A���a�ɂ͎��������ƁA����}�j�A�̑]�ǂ̋����Ɗ������`����Ă���̂ł��B
�@����Ɗ����܂��B�]�ǂ̐^�ӂ͂����ɂ���Ɗ����܂��B
�@���a�����ĂȂ��҂ɂƂ��Ă��A���a�����Q�肵���҂ɂ��A���߂͈���Ă��A
�@���ꂼ���������߂ł��A�]�ǂ̋�ƘA�����Ă��āA������������ǂ���Ǝv���܂��B
�@����D���Ƃ��ẮA���̋傩��́A�m�Ԃ����a�̌��O���悶�o�����Ԃ�G�炷���i�������Ԃ̂ł��B
�@�����ԂŐ@�����肵����A������ρA���a�����𗣂����u�ԁA���a����]�������Ă��܂��܂���B
�@�O�̂߂�̐��ł́A���͓��a�ɐڂ��Ă����Ԃɂ͗����܂���B
�@���O�ɓo��O�A�o���ė��������A���肽���̒����̎p���Ŏ肪�ӂ������Ă��Ȃ���A�Ԃş���@���܂��B
�@�������A�o��O�Ɋ������N���C�}�b�N�X�ɒB����͂��͂Ȃ��ł��B
�@���a�̓����Ɏ���A���̐��̂ƑS�̂����n���������A������N���C�}�b�N�X�ł��傤���A�������ł��傤�B
�@�܂��A�o��������ƁA���肽���́A�Ԃ����ɔG���O�ɁA���łɌ�_���ł��ԔG��ɂȂ��Ă��܂��B
�@����D���Ƃ��Č��n��̌�����Ə�L�̉��߂Ɏ���܂����A
�@�]���̉��߂ł͂Ȃ��A���̉��߂̂ق����������Ɩ����Ɏ��M�������܂��B
�@����D���̕��X�A���^�����������܂����ˁH
�@�@����̐_�l�̌���ɑ喞���@�@�@�@�@�@�@�@�B�e�֎~�ł����A�p���t���b�g�ɂ͌��O�̈ꕔ���ʂ��Ă��܂��B�B�B
�@�@�@
�@
�@
�@�Z�@���V�{���a�R�_��
�@�@�@�E���{������Q���Q
�@�Z�@�s���@�ՂƌܐF���i���a�R��^�m�ԋ��j
�@�Z�@���a�R�L�����H
�@�Z�@��l��
�@�@�@�E���g�ŏC�s�V�n
�@�@�@�E���a�R�Q��i�O���z���_�����C�j
�@�@�@�E�ʕP��א_��
�@�Z�@��l��{�{�����Q���܂łܑ̕���
�@�@�@�E���F�����C���̕���
�@�@�@�E�{�{�Q�w�o�X
�@�@�@�E��^����
�@�@�@�E���̒r���� �O������_��
�@�Z�@���a�R�̂��R��
�@�Z�@���a�R�_�Ж{�{
�@�u���a�R�匠���ɒʂ���{���ƂȂ��v�ƍO�@��t������ĊJ����Ɠ`������{�����ł����A
�@�_�������߂ɂ��{�����͎�����ԏサ�A���a�R�_�ЂƂȂ��Ă��܂��B
�@����112�����ɖʂ��āA������ՂɁu�{������Q���Q�v������܂��B
�i�����j
�u���a�R�_��
�@�����R�{�����͐_�������߂ɂ��A����7�N(1874)�Ɏ�����ԏサ���a�R�_�ЂƂȂ����B�{�����͍O�@��t�̊J�R�Ɠ`�����A�]�ˎ���ɂ͓��a�R���ʓ��Ƃ��Ĕɉh���ɂ߂��B�o�H�O�R�Q�q�L�u�O�R�w���́v�ɁA�{�����ɂ��āu�{���͓�\�܌��l�ʂɂāA�O�t�O������F��ʂ��Z�߁A���Ɍ��\�v�ƋL���Ă���B�������������N(1868)�̕�C�푈�̍ہA���ɂ�����剾���͏Ď������B���݂̖{�a�͖���22�N(1889)�̍Č��ł���B�v
�@�@�@
�@
�@�������̐����ɂ́A���썑�̓ߐ{�S�A���J�S�A�͓��S�̕����������܂��B
�@��Q�́A�M�҂��{�����Ɋ�i���A�{�������A�M�҂ɑ����ē��a�R�֑�Q�F�肷����̂ł��B
�@�M�҂͌�D�i��F���D�j���܂��B
�@�{�����ł͐M�҂ɑ��A���N�R��B���o�������āA���D�i��F���D�j��z���Ă��܂����B
�@�Ȗ̐ڍ��̓��S���i�ڍ��،����فj���A�܂��ɂ���ł��i�ʓr�L�q�j�B
�i�����j
�u���쒬�w�蕶�����@����{������Q���Q
�@�@�����\���N�\��\����
�@���a�R�M�҂����萬�A�̂��߁A���z�̋��K��ʓ����Ɋ�i���A�Z�E�ɑ�Q���˗�����M�`�Ԃ��������B���̍ہA��i�z�̈ꕔ�ɂČ������ꂽ�̂���Q���ł���B
�@��Q�͖����A�Z�E���{�������ɂċF�����A���a�R���O�ւ͐�B�C�������킵�ĎQ�w�����A�M�҂ɂ́u���a�R���D�v��z�z�����B
�@��Q���Q�̌����͏\�����I�㔼�ɏW�����Ă���A�����ɂ͎���m�F����Ă���B��i�҂͓Ȗ،��̓ߐ{�S�A�͓��S�A���J�S�╟�����̈��B�S�̍u���ł��邪�A���쒬�g��̏��c�����q������̈�l�ł���B
�@���a�R�i����䋟�c��i�v�͓ߐ{�S�̕S�����ɂ킽��O�����A���i�ܔN�i�ꎵ���Z�j�A���������i���c�܌ܗ��A�Δ�E�J�ዟ�{�����A���D���ܗ��j����i���A�����̑�Q���˗��������̂ł���B
�@�@���쒬����ψ���v
�@�@�@
�@�@�@
�@
�i�����j
�u�s���@�ՂƌܐF��
�@�ܐF���ӂɂ͋���ȕs��������(����2.7m)�Ƒ���@����(����2.4m)���J���Ă����B
�@�����Ƃ��u�����Y���ŁA�]�ˎ���̒����ɕ������̐M�҂���i�������̂ł��������A�������N�̔p���ʎ߂ɂ���Ď�蕥��ꂽ�B
�@�����ɂ́A�u���a�R�v(�Éi5�N[1852])�u�����^���ܕS�ݕՋ��{�v(����5�N[1822])�u�����s
���C�v(����2�N[1855])�u�m�Ԃ̋��v�Ȃǂ̐Δ�A����ɌܐF���ɂ́u�ٓV�l�v�����J����Ă���B�v
�@�@�@�@
���m�ԋ�聄
�@�u�_�̕�����Č��̎R�v
�@�@�@
���ܐF���ƕٓV�l��
�@�@�@
�@���a�R�Q�ď����������a�R�L�����H�̗������̎�O��
�@�u���a�R�h�ɂ�ǂ̂�܁v�i����23�N�Ɂu���a�R�قĂ�v���u���a�R�h�ɂ�ǂ̂�܁v�j������܂��B
�@2011�N�̐�Q�ŋx�ƒ��ł��B2018�N�ɕقƂȂ�܂����B
�@�@�@
�@������ʂ��^�c���铒�a�R�L�����H�ł��B
�@�������ŁA�����ʍs���ƒ��ԗ���400�~���x�����܂��B
�@����K�����x30km�W���ł��B
�@�@�@
�@
�@�L�����H�̏I�_�́A�咹��(����18���B����5�N(1993)10���v�H)������l��ł��B
�@�y�̗X�֎Ԃ͓o���Ă����܂������A��ʎԂŏ���̂͂����܂łł��B
�@�@�@
�@
�@�@�@
�@���a�R�̍s�҂��A��l������̏�Ƃ��܂����B
�@�Δ�u���g�ŏC�s�V�n ���a�R��l�V�v
�i�����j
�u�R��
�@���a�R�͏o�H�O�R�̉��̉@�Ƃ��Ė����̏��߂܂Ő_�ŏK���̗�R�Ƃ��ĉh�������A��l��͖ؐH�s�l�i�ꐢ�s�l�j�C�s�̗�n�ł���܂����B
�@�����n���ɂ��鑦�g�ŘZ��
�@�@���@�C��l�@����V�@���������
�@�@�S��C��l�@���A���@���������O�|
�@�@�{���C��l�@�{�����@����������{
�@�@�S���C��l�@��x���@�߉��s
�@�@���C��l�@�@�C�����@��c�s
�@�@�~���C��l�@�C�����@��c�s
�@�́A�F���a�R��l��ɉ��Č܍���f���\����f���Č������C�s���d�ˏO���ϓx�̂��ߒ�g���ꂽ�������X�ł���܂��B�ŋ߂��̗��A���a�R��l��̐M�j�ւ��L���������ė~�����Ƃ̗v�]��������A�f��u���R�v�ɉ��ă~�C�������쐻�����䉏�Œ߉��s�o�g�㔎�H�R����Y�����͋[���̕�[������܂����B����̎���œ��a�M���M�d�Ȏ����ł���܂��B�@���a�R�{�{�v
�@�@�@
�@
�@����17(2005)�N�ɊJ�R1400�N���}���A�{�{�����Ɂu��_���̑����v���݂����܂����B
�@�܂��A��l��̎Q�ď����Ɂu�O���z���_�����C�v���ݒu����܂����B
�@�@�@
�@
����ʗ�����
�@���ꂪ��ʗ����ƌ�_���ƂQ�J������A�ŏ��͈�ʗ����ɍs���Ă��܂��܂����B
�@��ʗ����́A�������ւ̂��������̎��̐�̗������ƁA�z�����̐�́A�����ɐԒ��F�ɐ��܂��Ă���A
�@����ł͂Ȃ��̂ł��傤���A�S���܂ނ����̐��ł͂Ȃ��悤�ł��B
�@�@�@
�@
�@
������
�@��ԊK���̌�_���֍s���܂��B
�@�O���z���_�����C�́A�O������_�Ђ���N�o���錹�����������_���ł��B
�@���u���a�R��l�V����O������_�Ќ���v
�@�ܓ�_���Y�f�E�S�i�U�j�|�i�g���E���E�J���V�E���|�������E���_������
�@�u�O���v�Ƃ͐�����Ӗ����A���͏��̔��ʐ����ɂ͐���̋L�ڂ�����܂��B
�@�@�@
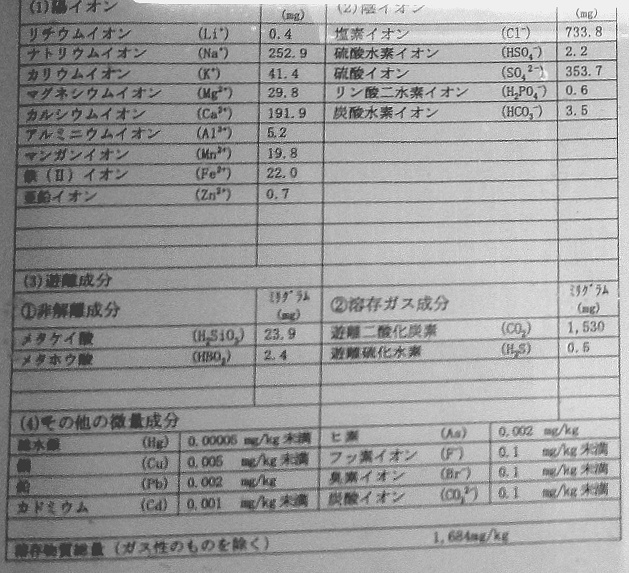
�@���ň��܂��A�Y�_�������āA�S���ŁA�}�Y���I�ł��B
�@�{�{�����u��_���̑����v�̕��͏����f�����Ă��܂����B
�@�������u�o����_����v�B13.690g�̋���������ł��B
�@�@�@
�@
����_���^�Гa���ΑK����
�@���D�́A���M�����̂��������ł��B
�@�@�@
�@
�@�������ɎГa���݂����A�ΑK�����ݒu����Ă��܂��B
�@�������ɐ_�Ђ��J���Ă���͓̂x�X�ڂɂ��܂����A�ΑK���͏��߂Č��܂����B
�@�@�@
�@
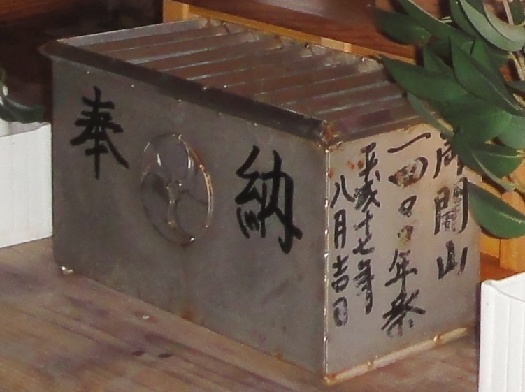
�i�����j
�u�O���z���_�����C�̗R��
����@�@�O������_��
��Ր_�@�O���s�����_
�@�������a�R�Q�ď���蓒�a�R�_�Ж{�{�Ɍ������Q���ɂ͏\���Ђ̌䖖�Ђ��������Ă���܂����A����Ђɐ��̐_�l�ł���܂��O������_�Ђ����J�肳��Ă���܂��B�×��O���z��Ə̂��A���x�\���x�̒Y�_�z���ł����X�ƗN���o�Ă���A�S����育���h���Ă���M�̏A�ے��Ƃ��āA��{�{�̌�_���Ƌ��ɂ��Q�w�̊F�l���p�����Ă���܂����B�܂��A���a�ɓ���܂��Ă��z��̋߂��Ɋ���������c�܂�A�Q�w�҂ɒO���z��̂����C�ƎR�Ȃǂ̎R�̍K����Ă���A�ŋ߂̒����ł��A�w�l�a�A�ݒ��a�A���A�a�A�얞�ǂȂǂ̌��\���F�߂��Ă��܂��B
�@�����\���N�́A���a�R��J�R��l�Z�Z�N�̉��N�ɓ�����A��_�l�̍X�Ȃ��_���̐�g���v��A�v�X���̐l�X�̍K�����肢�A���̌̎��Ɉ�(����)��ŒO���z���_�����C��V�݂������܂����B
�@���Q�w�̊F�l�ɂ͐S�Â��Ɍ�_���ɐZ��A���a�R��_�l�̂�����̂���ƁA��͂Ղ���܂����Ƃ�O���鎟��ł���܂��B
�������p���ԁ@�ߑO�\�ꎞ�`�ߌ�O���@�ߌ���`���㎞
�@��_�����C�͐_�l�̌�_���ɓ���A�S�g���ɑ�_�l�̌�_�������Ƃ��|�Ƃ��Ă���܂��̂ŁA�������ɂ͓��D�Ɛ_�I�����邾���ł��B��A�V�����[���̐ݔ��͂���܂���̂ł��������������B
�A�|���蓒�����Ă�����肭�������B
�B���D�͈�x�Ɏ��A�����������قǂł��B
�C������̓����͂��������������B
�������p���ԈȊO�͈�K�ɒʏ�̓�\�l���ԗ��p�̗������������܂��B
�������ɓK�������x�ɕۂ��߉������Ă���܂��B�v
�@�@
�@���a��_�Ɋ�|������l�́A�܂���l��̋ʕP��ׂɂ��Q�肷��Ƃ����K�킵������܂����B
�@���a61�N���c�̎Гa�̗��ɂ���Β������̖{�ЂƎv���܂��B
�@�@�@
�@
�@
�i�����j
�u�ʕP��א_�Ђ̗R��
�@�ʕP��א_�Ђ́A������l��̗��ɉ����āA���g���ł̏C�s�ɒ�g���ꂽ�S��C��l�����_�Ƃ��ċA�˂���A���̌���Đ��ł��ꂽ�Ƃ̂����ɂ�蓒�a��_�Ɋ�|������l�́A�悸�ʕP��ׂɂ��Q�肵�A���̗쌱�ɂ������肵�A���̂����������Ė{���B������Ƃ����A�K�킵������܂����B
�@���߂́A�Β���ߑ�Ƃ��Ă���܂��������a61�N�_�Ђ̌�_���ȂĎГa�c�����A�M�҂̊�i�ɂ�蒹������������A��Г���V�̐��������܂����B
�@�@�ʕP�݂̂��Â������ނ܂ߐl���F��^�S�Â����ւƁ@�t�x�v
�@�@
�@�{�{�Q�w�o�X�����铹�H�ɂ͕����̈�Ƃ��ĉ��F�����C����������Ă��܂��B
�@�@�@
�@
�@�{�{�����Q���܂ł́A��l��{�{�Q�w�o�X�łT���قǁi�Г�200�~�A����300�~�j�ł��B
�@�k�����Ə�����ʂ̐����ɂ���30���A�ē�����20���B
�@�s���̓o�X�ɏ��A�A��͕����܂����B
�@�A��́A���F�̐��Ɏ��������A���������肵�Ȃ��牺��܂����B
�@15���قǂŐ�l��ɒ����܂����B
�@�@�@
�@
�@�u����v�́A������ɂ�������O�̉E��ɂ���u�퐢�v�ߌ˕P�_�Ёv�������ł��B
�@�_�Ђ���������u����i�����킪���j�v�͗�������֎~�ƂȂ��Ă��܂��B
�@��ɂ́A�����ǂ������܂��B����u�O������_�Ёv�̓����ǂł��傤�B
�@�@�@
�@
�@
�@�@�@
�u���̌��� ���_�Ёv�u��l���� �V�_�Ёv�u��t�@��
��t�_�Ёv�u�D�k���� �퐢��P�_�Ёv�u���V��ߗ����̑����쌠�� �Y��_�Ёv
�@�ܑ��������ɂ��������Ђł��B
�@�@�@
�@
�@
�@
�@���̒r�Ƃ́A�S���ŐԂ��Ȃ����z��̐F����݂��Ă��̂ł��傤�B
�@���n�ɂȂ��Ă��āA���ꗎ���Ă��鐅�Ɏ�������݂܂����A�₽���ł��B
�@��������Ɖ��h���͂���܂���B
�@���h�����O�̓��Ƃ͕ʖ��Ƃ������Ƃł��傤�B
�@�����߂��́u�W�����v������Ԓ��F�̐������ݏo�Ă��܂����B
�@�@�@
�@
�@
�@�������牺���̌�̎�O�ɁA���F�ɐ��܂�S����тт��ꂪ���ꗎ���Ă��܂��B
�@��������ނƗ₽���ł��A��������Ɖ��h���͂���܂���B
�@�@�@
�i�����j
�u���a�R�̂��R��
�@��Ր_�@��R�_���i������܂Â݂݂̂��Ɓj�@��ȋM���i�����Ȃނ��݂̂��Ɓj�@���F�����i�����ȂЂ��Ȃ݂̂��Ɓj
�@�o�H�O�R�Ƃ́A���R�E�H���R�E���a�R�̑��̂Ő��ÓV�c���N�i593�j�A��O�\��㐒�s�V�c�̌�q�ł���I�q�c�q�l�̌�J�R�ł���B�c�q�́A�h�䎁�̓������A���s�̗R�ǂ���C�H���o�āA�o�H�������l�̗R�ǂɓ���ꂽ�B�����ĎO�{���̗쒹�̓����܂܂ɉH���R�ɓ����s��s�̖��A�H���R��ɉH�������̌䎦����q���A�����ŁA���R�A���a�R���J���A���_���H���R�Ɋ������ĉH���O���匠���Ə̂����B
�@���̌�A�c�q�̌䓿��炢�A���ꔒ�R���J�����א���l��C�����̑c�ƌ�������̍s�ҁA�܂��^���@�̊J�c�O�@��t�A�V��@�̊J�c�`����t�Ƃ��̒�q���o��t�Ȃǂ����R���ďC�s�������Ƃ��`�����Ă���B�������čc�q�C�s�̓��͎���ɔ��W���ĉH���h�C�����ƂȂ�A�S���ɖ���m��ꎞ����d�˂�ɂ�A�l�X�̌����M���W�߂邱�ƂƂȂ����B
�@�����A���a�R�́A���Ï\�O�i605�j�̌�J�R�Ƃ���A�o�H�O�R�̑����̉@�Ƃ��ē��Ɍ����M���W�߂Ă����B�]�ˎ���܂ł͐^���@�Ƃ��ĕ�d���Ă������A�����ېV�ɍۂ��Đ_�������i�p���ʎ߁j�����߂���A�Âւ̐_�ޔ��R�ɂ�����_�ЂƂ��ĕ�d���Ă���B
�@��ɏo�H�O�R�M�́u�O�֎O�x�v�i����ǁj��u�[���Đ��v�i�������������j�ȂǁA���܂�ς��̐M�����������Â��Ă���B�H���R�Ō������v�̌�_���ɗ^��A���R�̑�_�̉��Ŏ���̑̌������A���ߐ[�����a�̑�_���A�V���������������āA�Đ�����ƍl������B
�@���ɓ��a�R�ł̏C�s�͎O����������@����{�n���Ƃ����R�_���E��ȋM���E���F�����̗쌱�ɂ��A�_���ƈ�̂ɂȂ葦�g�����邱�Ƃ��o����Ƃ��ꂽ�B�܂����a�R�{�{�ł́A��_�̂�ڂ̓�����ɔq���A���ɐG��Ă��w�肪�o�����쌱�̗L�����A�o�������m�Ԃ��u����ʓ��a�ɂʂ炷�Ԃ��ȁv�̋���c���ꂽ�A�×��u���Ȃ���v�u�����Ȃ���v�Ɖ��߂�ꂽ����_��̗��Ȃ̂ł���B
���Q�q�ɂ���
�E�Q�q�o�X���~��A���a�R�_�Ж{�{�Q���������k���ܕ��i��S���[�g���j
�E�{�{�����őf���ɂȂ��Ă��P�����Ă����_�O�ɐi�݂��Q�艺�����B
���P���@�܁Z�Z�~
���{�{���͂��R���ɂ��B�e�͂������������B�v
�@�@
�@�{�{�Q�w�o�X���~��A�{�{�Q����������100���Ŗ{�{�ł��B
�@���R�ւ̓o�R���ւ̓r���ɔm�ԂƑ\�ǂ̋�肪����܂��B
�@�m�ԋ��u����ʁ@���a�ɔG�炷�@�Ԃ��ȁv(���a30�N(1955�N)10������)
�@�\�Nj��u���a�R�@�K���ޓ��́@�����ȁv(���a39�N(1964�N)10������)
�@�m�ԋ��̍����ʂɂ́u�ċ��v�ƍ���ł���܂����B
�@���āA���P��̉��̏����őf���ɂȂ�A���P��500�~��[�߁A
�@���̐l�`�i�ЂƂ����j�Ƃ����D�u���a�R�_�Ќ��P��v��n����܂��B
�@���P�����A���̐l�`�i�ЂƂ����j�ŁA�����ő̂��ȂłĐg�̉����l�`�Ɉڂ��A
�@�l�`�ɑ��𐁂��������ɗ����܂��B
�@�{�{�֓��邱�Ƃ�������A�\�ǁu���a�R �K���ޓ���
�����ȁv�̓���i�ނƁA���O�B
�@���O�̍������荞��Ŕw��ɍs�����Ƃ��ł��A���O�̓��̗N�o�������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�u�E���ʍs�ł��I�K�i�͋A��p�ł��I�v�ƁA�Ж����̕�������������ʐ������Ă��܂��B
�@�M���������ɓ`���܂��A��������Ɖ��h���{�S���ł��B
�@��������M�����N�o���A�����F�̕��ł��B
�@��_�̂ɐG�ꂽ�肷�邱�Ƃ͋ւ����Ă���̂���ʓI�ł����A
�@�����ł́A��_�̂ɑf���œo������A����������A�w�ォ�瓒���N���o��l�q��������ł���Ƃ�
�@�������̂ł��B
�@�ʐ^�B�e�֎~�Ȃ̂ŎB��܂��A���O�̌`��͌��܂���i����Ȃ�̗��R���B�B�j
�@�o�H�O�R�_�Ђ̃p���t���b�g�ɂ͒��F�̌��O�̈ꕔ���ʂ��Ă��܂��B
�@������ʂ̒ʍs���ɂ́A���P���̎ʐ^���f�ڂ���Ă��܂��B
�@���Ԃ��������ĕ��ɂ����u�������v��500�~�Ŕ����Ă��܂����B
�@��������߂܂����i300�~�j�B
�@���Q�肪���ނƁu���a�R�o����_�����v�i���F�o����_�j������܂��B
�@��������B���̗����͏�̗����̃I�[�o�[�t���[�B
�@�o����_�̐Δ�̂Ƃ��납�猹���B��������Ɖ��h���{�S���B
�@��_�̂ł̎��R�����̂ق����������̂ł����B
�@�@�@
�@
�@